|

[ ペーパーバック ]
|
An Atlas of Animal Anatomy for Artists
・Wilhelm Ellenberger
【Dover Pubns】
発売日: 1956-06
参考価格: 1,740 円(税込)
販売価格: 1,162 円(税込)

|
・Wilhelm Ellenberger
|
カスタマー平均評価:  5 5
 実用だけでなく、素敵な「オマケ」としての後半部分。 実用だけでなく、素敵な「オマケ」としての後半部分。
哺乳類の解剖図集。馬、犬、ライオン、牛、ヤギ、鹿、イエネコ、猿、アザラシ、ウサギ、ネズミ、ムササビ、蝙蝠の図版が収録されています。
後半の図版、特に猿のページ以降のものは古い文献からなので、美術用ならば実用には向かないかも知れませんが、資料としては興味深いものではあります。
これらは、かの有名な博物・分類学者キュヴィエ・ジョルジュ
(巻末の資料を読む限りでは、彼の死後、1849年に発行されたAnatomie Compareeからの引用のようです。1800年発行の研究書Lecons d'anatomie compareeに同じ図版が載っているかはちょっと確認できません…)
の名がついている資料なので、いずれ絵画など文化的な目的で本書を購入なさるならば、これらはそれなりに魅力的な「オマケ」になるかと思います。
 粘土細工にも最適 粘土細工にも最適
絵はもちろんのこと、粘土・彫刻等の製作においても非常に参考になります。
「ありもしない想像の筋肉を付けてしまい、イマイチリアリティーに欠ける」といった作品にはならないでしょう。
基礎骨格が理解できることにより、デフォルメした動物を書くときにも特徴を捉えた良い作品が完成することと思います。
 筋肉と骨のみ 筋肉と骨のみ
馬、ライオン、犬、牛、ヤギの骨格と筋肉が精密な絵で載っています。
動物の動きの解析はまったく無く、骨と筋肉の図版のみです。
おまけとしてこうもりや猿などのものもありますが、こちらは本当におまけ程度です。筋肉と骨の名前がほぼ網羅されているので、馬とライオンの骨格を比べたり、
人間のものと照らし合わせたりすることができて理解しやすかったです。
 良書 良書
犬 ライオン 馬 ウサギ等の骨格や筋肉が癖の無い図版でパーツごとに分かり易く載っています 図版も大きくとても見やすいです
オススメです!
 なかなかない本 なかなかない本
馬、犬、ライオン、牛、鹿類とヤギを中心に、とても詳しい骨格や筋肉などの図版がそれぞれ10枚以上載っています。パーツごとにいろいろな角度からの資料もあるので、動物の絵や造型にはとても役にたつと思います。
|
|
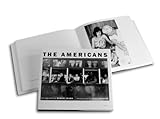
[ ハードカバー ]
|
The Americans
【Steidl】
発売日: 2008-05
参考価格: 4,031 円(税込)
販売価格: 3,588 円(税込)

|
|
カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 リアルなアメリカ リアルなアメリカ
写真好き アメリカ好きには、是非とも1冊手元に置いといていただきたい。1枚1枚の写真には、撮影された場所の地名の記述がある。地名と一緒に写真を見てもらうと、写真の良さがスゴく伝わると思う。例えばシカゴは政治的な匂いのする写真が多いし、ニューヨークは様々な変わった人たちがいるイメージ。キャロナイナは何か精神的な感じがする。行ったことはなくても、写真から伝わるイメージが凄い。そしてどこか物悲しげな雰囲気も、リアルなアメリカを捉えたロバートの写真の良さだと思う。
 マイノリティ マイノリティ
アメリカ国旗を巧みに取り込んだショットが
やはり印象に残る
マイノリティを意識したショットも多い
自動車のカヴァーのショットは
鈍い光を放っている
 ボクのバイブルというべき一冊 ボクのバイブルというべき一冊
日本語!である「コンポラ写真」の語源「コンテンポラリー・フォトグラファーズ」と混同されやすいようだ。ロバート・フランクはこの写真集にジャック・ケロアックが序文を寄せているように、50年代に一世風靡したビートニク世代といえる写真家である。いわば上記の写真家たちに影響を与えた人といったほうが正確である。ロバート・フランクは924年スイスのチューリヒ生まれ。グッゲンハイム財団の奨学金を得て1955年から1956年にかけてアメリカ各地を旅行し、その生活をシビアな目で捉えた。その記録がこの伝説のというべき写真集に結晶されている。1958年パリのデルピル社から、翌年アメリカ版がグルーブ出版から刊行された。再版がスカロ社から出ている。撮影データは不明だが、おそらくライカによる撮影であろう。ボクのバイブルというべき一冊である。
 写真史で外せない一冊 写真史で外せない一冊
ロバートフランクはウォーカーエバンスの写真を意識して撮ったと言われています
8×10で撮ったウォーカーエバンスのアメリカ 35ミリで撮ったロバートフランクのアメリカ この共通点を探すのと写真表現の難しさそして面白さと奥の深さが何とも言えない デジタル化が進む中で写真というもの本質を考える事の出来る、外せない一冊だと思います
 ロバートフランクを一躍有名にした一冊 ロバートフランクを一躍有名にした一冊
The Americans でRobert Frankは一躍有名カメラマンになった。どの写真もAmericaの裏面、華やかで豊かなアメリカからは隠された、貧しくて恵まれない人々の日常が刻まれている。 この一冊を読むことで、読者はカメラマンとアメリカの旅を経験する。そして、悲しくて暗い写真の中に、カメラマンの暖かい心を読み取る。 現代写真の基本の一冊
|
|

[ マスマーケット ]
|
Word Power Made Easy
・Norman Lewis
【Pocket Books (Mm)】
発売日: 1991-02-15
参考価格: 1,015 円(税込)
販売価格: 627 円(税込)

|
・Norman Lewis
|
カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 極上のボキャビル本 極上のボキャビル本
この著者のボキャビル本はどれも、やっていて最高に楽しいし本当に覚えやすい、忘れにくい。この本に出てくる語は、英検1級を既に取得したという方でも知らない単語がほとんどだと思うのでやる価値有りです。Instant Word Power (Signet)
 完走するまで頑張りました。 完走するまで頑張りました。
本文中の「この本をやる前と後ではあなたは、もはや同じ人間ではない…そうであるはずがないのだ!」という文章を励みに約1ヶ月で最後までやり終えました。もちろん、完璧に覚わっているわけではないのでまた復習し直しますが。すごいです、この本をやり終えた今の気持ちは。あと3セッションくらい、という最後の最後で止めてしまいたくなるのですが、なんとか頑張り通しました。
英検1級Pass単熟語の見出し単語がかなり基本的に見えてきました。実用的な面から言えば、これらの単語は使わなくても済むんでしょうが、今まで挫折したペーパーバックをめくるとその時、辞書で調べて意味が書いてある単語をほとんど知っています。「単語が先か多読が先か」という問題が中級から上級者には必ずあると思いますが、上級に行くためにはある時期、徹底してボキャブラリーと格闘すべきだと自信を持って言えます。
洋書ボキャビルの本を何冊か持っていますが(やり通したのはまだわずか)、どの本にも「ボキャビルをすると頭が良くなる」とか、はたまた「ボキャビルを増やすことで年収が上がる」とか、ボキャビルとの相関関係にこれだけ自信を持っているのが羨ましく思います。
 ちゃんとした英語を読み書きするための本 ちゃんとした英語を読み書きするための本
著者が本の中で述べているように、アメリカで教育水準の高い人たちが使う(あるいは理解できる)単語、文法を想定して、それらについて丁寧に解説しています。日本の受験英語で学んだことと異なる文法上の見解なども随所にあり面白く読めます。(例、日本ではfurtherとfarther、prettyとveryなど選択問題で出てくる「間違えやすい意味の単語」がアメリカの英語学者の多数の見解としては実は「同じ意味の単語」として扱われているなど)実はこの本は2冊目で10年近く使った1冊目がボロボロになったので買い替えました。なかなか100%は覚えられません。
 すばらしい作りの単語帳 すばらしい作りの単語帳
最も効果的に語彙を増やすことを謳っている通り、まともにやれば効果は非常に高い。ページ数が多いが、著者の親切心からなのだと感じれるようになると良さが理解できる。
基本はアウトプット中心の教材であり、日本で出版される受験用の単語帳とはまったく雰囲気が異なる。簡単な説明の後すぐに、新出単語とその定義を結ぶ問題であったり、実際の例題だが、gerontologist(a person who studies the process of people growing old)について、
A gerontologist is interested in the non-medical problems of adolescence. TRUE or FALSE? と聞かれたり。そうやっているとだいたい単語になじんでくるが、その後次の新出単語に入るのかと思いきや、さっき扱ったばかりの単語の語源の説明と、その派生する単語の説明が入る。そしてまた上記のような設問。
ここまでinput output繰り返せば、まったく知らない単語でも嫌でも頭に入っている。とにかく作りがとても親身で、日本の受験用含め8冊くらい単語帳は持っているが、やっていて飽きないし、覚えれるチャンスをくれる単語本はこれだけである。
 学習意欲を持続させる本 学習意欲を持続させる本
子どもの頃は、なぜ?という知識獲得のための道具としての言葉(単語)を知識と一緒に
増やす事が簡単でした。でも大人になって知識獲得の「なぜ?」はなくなって行きます。
この本は子どもの頃の「なぜ?」を大人に取り戻し学習意欲を持続させて英単語を学習し
記憶させて語彙数を増やす目的で書かれています。単純に英単語を覚えるというより英単語と
それに関係する知識を読ませる事で英単語数を増やしていく感じでした。
英単語のレヴェルは普通より高い感じです。英語がすきな人は最後まで読めると思います。
|
|

[ ハードカバー ]
|
Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism
・George A. Akerlof ・Robert J. Shiller
【Princeton Univ Pr】
発売日: 2009-01-29
参考価格: 2,170 円(税込)
販売価格: 2,240 円(税込)

|
・George A. Akerlof
・Robert J. Shiller
|
カスタマー平均評価: 0
|
|

[ CD ]
|
7 Habits of Highly Effective People (3CD)
・Stephen R. Covey
【Franklincovey】
発売日: 2001-10-01
参考価格: 2,270 円(税込)
販売価格: 2,689 円(税込)

|
・Stephen R. Covey
|
カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 社会人への入門書 社会人への入門書
少し分厚いですが、とても読みやすく一気に読みました。
自己啓発書のような内容で、当たり前のようで気づいてない、
もしくは忘れがちな、社会人として大切な事を要約しまとめた一冊です。
たとえ話や噛み砕いた説明で、固い文章が苦手!
といった方でもすんなりと読めます。
学生のうちに読んでおきたい1冊です!
 全ての自己啓発本の原点 全ての自己啓発本の原点
全世界で1500万部ほど売り上げている自己啓発本の原点。
最近、ファストフードのように食べやすく加工された薄い自己啓発本が乱発されていますが、それらの書籍を100冊乱読するより、こういう骨太の名著を熟読する方が価値はあると思います。
この本で貫かれている価値観は「インサイド・アウト(自分自身の問題が先にあり、その後に外の問題がある」)という考え方。
自分はなんで理解されないのか?などと感じている人などは、この本に書かれているインサイドアウトの考え方を理解するとすっきりするんじゃ無いかと思います。
自分の成長度合いに応じて、理解が深まる本に仕上がっているので、時に応じてたびたび読んでみたいと思います。
 まずは最初の3つの習慣だけでも まずは最初の3つの習慣だけでも
習慣の数は7つと少ないが、私も含めて、どれくらいの人がこの習慣を実践できている
だろうか?
特に第1の習慣である自己責任は、人間の本能に逆らうのか、自分に起きた悪いことを
上司、会社、家族や社会など周りのせいにしている人が、とても多いように思う。
まずは、最初の3つの習慣の、自己責任、目標設定、優先順位づけを実践するだけでも、
人生が劇的に前向きに変わると思う。
厚い本だが、書かれている原則そのものはとてもシンプルだ。
本当の挑戦は、その原則を実践することにある。
 成功哲学理論の決定版? 成功哲学理論の決定版?
これを超える書物があるならば、是非教えて頂きたい。
ここまで読んでいて納得感があると思った書物は無いかもしれない。
生活の中心に関する、自己中心・お金中心の記述が薄いかなとは思った。
 CDだけですよ CDだけですよ
てっきりCD付の商品だと思ったら
CDのみでした。
なんでCDのみの商品が洋書部門で1位なんでしょうか?
皆さん気をつけてください。
|
|

[ ペーパーバック ]
|
7 Habits Of Highly Effective People 15th Anniversary Edition
・Stephen R. Covey
【Free Pr】
発売日: 2004-11-09
参考価格: 1,602 円(税込)
販売価格: 1,432 円(税込)

|
・Stephen R. Covey
|
カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 社会人への入門書 社会人への入門書
少し分厚いですが、とても読みやすく一気に読みました。
自己啓発書のような内容で、当たり前のようで気づいてない、
もしくは忘れがちな、社会人として大切な事を要約しまとめた一冊です。
たとえ話や噛み砕いた説明で、固い文章が苦手!
といった方でもすんなりと読めます。
学生のうちに読んでおきたい1冊です!
 全ての自己啓発本の原点 全ての自己啓発本の原点
全世界で1500万部ほど売り上げている自己啓発本の原点。
最近、ファストフードのように食べやすく加工された薄い自己啓発本が乱発されていますが、それらの書籍を100冊乱読するより、こういう骨太の名著を熟読する方が価値はあると思います。
この本で貫かれている価値観は「インサイド・アウト(自分自身の問題が先にあり、その後に外の問題がある」)という考え方。
自分はなんで理解されないのか?などと感じている人などは、この本に書かれているインサイドアウトの考え方を理解するとすっきりするんじゃ無いかと思います。
自分の成長度合いに応じて、理解が深まる本に仕上がっているので、時に応じてたびたび読んでみたいと思います。
 まずは最初の3つの習慣だけでも まずは最初の3つの習慣だけでも
習慣の数は7つと少ないが、私も含めて、どれくらいの人がこの習慣を実践できている
だろうか?
特に第1の習慣である自己責任は、人間の本能に逆らうのか、自分に起きた悪いことを
上司、会社、家族や社会など周りのせいにしている人が、とても多いように思う。
まずは、最初の3つの習慣の、自己責任、目標設定、優先順位づけを実践するだけでも、
人生が劇的に前向きに変わると思う。
厚い本だが、書かれている原則そのものはとてもシンプルだ。
本当の挑戦は、その原則を実践することにある。
 成功哲学理論の決定版? 成功哲学理論の決定版?
これを超える書物があるならば、是非教えて頂きたい。
ここまで読んでいて納得感があると思った書物は無いかもしれない。
生活の中心に関する、自己中心・お金中心の記述が薄いかなとは思った。
 CDだけですよ CDだけですよ
てっきりCD付の商品だと思ったら
CDのみでした。
なんでCDのみの商品が洋書部門で1位なんでしょうか?
皆さん気をつけてください。
|
|

[ ペーパーバック ]
|
American Accent Training (American Accent Training)
・Ann Cook
【Barrons Educ Series Inc Audio】
発売日: 2000-09
参考価格: 5,798 円(税込)
販売価格: 3,588 円(税込)

|
・Ann Cook
|
カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 ちょっとおおらかな作りですが、良い教材です。 ちょっとおおらかな作りですが、良い教材です。
発音訓練の教材です。アメリカ製ですが、外国人向けにつくられているので難しくはありません。2周目に入っていますが、発音に悩んでいた私にとってはちょうど良い教材でした。
CDは5枚。ただし、最後の1枚は復習用。それ以外の4枚もナレーションがたくさん入っているので、その分を割り引くと特別量が多いというほどではないです。
前半は抑楊の練習。ここは音の強弱に合わせてゴム輪を伸ばしたり縮めたりしながらやります。これが結構長く続く。意外にここは日本人の盲点なので、一通りはちゃんとやった方が良いと思います。ただ、それにしてもちょっと多いかな。また、個人的には、
I didn't say he stole the money.
という文章を使った抑揚の練習が、潰れてしまった某大手英会話教室の上級用テキスト(Zone-G)にあったのと同じだったので、少し懐かしかった。きっと、古典的な例なのでしょうね。
全体的な作りとしては、いろいろおおらかなところがあります。重要なところとそうでもないなと思うレッスンが混在しています。1周やってそれがわかったので、2周目に入ってからはレッスンに応じて濃淡を付けてやっています。また、ノイズが入っているくらいならまだいいのですが、一部でCDとテキストが合っていないところもあります。一番いただけないのは、復習用の5枚目のCDです。内容は悪くないのに、70分超の復習がなんとたった1トラックに入っています。これには驚きました。この5枚目のCDで復習するのは実際はつらいと思います。少なくとも、私は途中で断念しました。あと、蛍光ペンと鏡は少し余計なお世話かな、その分もうちょっとコンパクトにして値段も安くしてくれたらいいのに、と思いました。
リエゾニングについては、専門のレッスン数自体は多くはないものの結構まとめて出てきます。ここはかなり繰り返してやりました。この部分についてはもっと詳しくて種類もたくさんあってもいいかもしれません。また、いかにも本場で作った発音トレーニングの教材だなあと思うこの教材の特徴のひとつとして、非常に巧みに韻を踏んだ意味としてはちょっとおかしい練習用文章を用いたレッスンがあちこちに出てくる点が挙げられます。ここまでのものは日本人の作る教材では難しいと思います。
尚、ひとつひとつの音の発音練習だけなら、日本の初心者用の教材でも間に合うと思いますし、実際そういうのを先にざっとやっておいた方が取り組みやすいと思います。
結論としては、いろいろ難点はあるし、ちょっとお高いですが、間違いなく良い教材です。
 見せ掛けの流暢さ、それでいいの? 見せ掛けの流暢さ、それでいいの?
私立理系卒業して、10年たったころ、米国勤務を命ぜられました
その当初は、米人が言ってることが良くわからず、
もちろん、自分で伝えたいことも伝わらず、悩んでいるときに、この本に出会いました。
・イントネーション(抑揚)
・アクセント(強勢)
・リエゾン(連結) を学びました。
一週間くらい勉強しただけで、効果てき面でした。
細かな発音はともかく、「抑揚・リズム」を理解しただけでも、
リスニングもスピーキングも見違えるほどになりました。
異国における生活の苦労を考えると、「命の恩人」みたいな本でした。
しかしながら、あれから10年経ち、考えることは、
この本では、「細かな発音」ができるようにはならないので、
「流暢になった」と自己満足陶酔していただけのように思います。
この本では、日本人の弱点のLやRの発音・聞き取りがうまくなるわけではありません。
恥ずかしながら、Rubber と Loverが100%区別できるとは現在でも言えません。
本書の「抑揚・強勢・連結」をマスターしただけでは、
「見せ掛けの流暢さ」しか実現できないということを理解して、
他の発音本を併用すべきです。
 アメリカ人らしい発音ができるようになります。 アメリカ人らしい発音ができるようになります。
本書は、アメリカ英語の
・イントネーション(抑揚)
・アクセント(強勢)
・リエゾン(連結)
を正しく身につけることを目的とした本です。
アメリカ英語では隣り合った音同士がリエゾンでくっついて消えたり一続きの音になることが多いので、日本語英語のように一語一語区切って発音してもアメリカ人に通じませんし、またアメリカ人が何を言っているのか聞き取れません。
本書は、どこがくっついてどの発音が消えるか、どこに抑揚・アクセントを置くかなどのルールを音声付きでわかりやすく説明してくれています。
本書を根気よくやる事で、英会話学校に通ったり留学しなくてもアメリカ人と十分コミュニケーションできる自然な英語の発音とアメリカ英語が聞き取れる能力が身に付きます。
本書で学習した後、アメリカのテレビやラジオを聴いたら、聞き取れる部分が多くなっている自分に感動するのではないでしょうか。
それくらい効果があります。
ただ、独自の発音記号に慣れるまでは挫折するかもしれないので少しずつCDを聞きながらやるのがよいかと思います。
欲を言えば、パッケージケースが巨大で置き場所に困るので書籍とCDを別売にしてほしかったです。5枚も付属CDがあるのですが、1枚紛失してしまいました。高価なパッケージなのでこんな時、CDが別売だと助かります。
 これ一冊でOK! これ一冊でOK!
米国に2年留学しており、個人的に大金を払って発音矯正に行きましたがやはりイントネーションなどの点で疑問点がありこちらの本の購入に踏み切りました。
発音の仕方(口、舌の動かし方)から始まると思いましたが、この本はまずイントネーションの基礎から学ぶのですね。大学受験英語などで出る項目なども全て載っているので受験生にもおすすめです。
ESL生徒むけなので、本文はそんなに難しい英語は使われていません。日本、フランス、ドイツ語との比較なども載ってて本格的だと思います。索引含め約200pありますが、CDも本文に沿ってあるので難なく学習が進められると思います。
口、舌の形に関しては全く知識の無い方には少々不足に感じられるかもしれません。もう一冊別の本、もしくはウェブサイトをみてみるといいかもしれません。
おすすめは "phonetics flash animation project"(Googleで検索)
です。American Englishをクリックすると舌の動きが動画でみれます。
大金払って発音矯正学校に行かなくてもこの本で間に合うと思いました。
非常に満足できる一冊です。
(現在では付属の5枚のCDはちゃんと袋に収められています。)
 ずぼらな作者 ずぼらな作者
エンクックさん。音声を録音してるときはMSNメッセンジャーなど音の出るアプリは終了してから録音したらどうですか^^?
彼女の日本語がちょっと笑える「ワタシは、そのオカネをヌスンデイマセーン」
|
|

[ ボードブック ]
|
Let's Play
・Leo Lionni
【Alfred a Knopf】
発売日: 2003-08-12
参考価格: 705 円(税込)
販売価格: 792 円(税込)

|
・Leo Lionni
|
カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 最初の洋書絵本♪ 最初の洋書絵本♪
1歳5ヶ月になる娘に最初の洋書絵本として購入しました。
文字数も少なくどんどん次へ次へめくってしまう娘にはちょうど良かったです。
まだまだ経験が少なく、反応は薄かったので★は4つですが、ボールで遊ぶところは喜んでいました。これからどんどん経験を増やして、「この絵分かる!」っとなればもっと反応は良くなると期待しています。
絵もとっても可愛くてLeo Lionniの他のシリーズも揃えたいです。
 オススメです オススメです
1才8ヶ月になる子供のために買いました。既に日本語の絵本はたくさん持っていましたが、
英語の絵本は持っていなかったので最初の絵本として与えました。最初は全く興味を示さずどちらかというと嫌がっていましたが、公園でボール遊びをする時などに絵本にあったよねなどと言って絵本のフレーズを使ってみたところ気に入ってくれたようで寝るときに「よんで」と持ってきました。
絵がかわいらしく本当に簡単な1行絵本なので、初めての1冊としてオススメします。
同時にA Color of His Ownも買いましたが、Let's Playの方がはるかに簡単です。
 初めての洋書絵本 初めての洋書絵本
タイトルと絵が簡単そうだったので購入しました。
子供に見せた初めての洋書絵本です!
購入してから子供(1歳半前)が毎日のように見るようになりました。
朝起きて一番に触るものが『Let's Play』でした。
親の私でさえ驚きましたが、絵本の中のワンシーンから「flower」という単語を発するようになったのです。
絵本の影響を目の当たりにした瞬間でした。
厚手の絵本で角もない為小さな子供でも安心して触らせれるのもよかったです。
 子供のお気に入りに 子供のお気に入りに
英会話の教室で使うために、先にLeo LionniのColor of his ownを買っていたのですが、それよりかは中に書いている文章の言葉数がずっと少ないので小さい子供への読み聞かせでも文を最後まで読む前にめくられるというストレスはありませんでした。本の裏にも書いていますが、6ヶ月から3歳くらいの子供にちょうどいいです。絵もかわいくて届いたその日に娘に何度も何度も読んでとせがまれました。Good morning! Good night! は私が読む前に先に言ってしまいます。
 シンプルでかわいい!! シンプルでかわいい!!
英語が大好きな娘の為に買いました。シンプルだけど、とてもきれいな色合いの絵で、娘以上に私の方が気に入ってしまいました。文章がとても短いので、3歳以下くらいのお子様にいいかも・・・。
|
|

[ Diary ]
|
Cath Kidston Birds Notebook
・Cath Kidston
【Chronicle Books】
発売日: 2007-03
参考価格: 1,004 円(税込)
販売価格: 993 円(税込)

|
・Cath Kidston
|
カスタマー平均評価:  4.5 4.5
 使いやすいノートです 使いやすいノートです
表紙がかなり厚手でしっかりした造りのノートです。
用紙も厚めでペンがにじんだりせずとても書きやすいです。
罫線の幅は7mmです。(赤でかわいい)
枚数は53枚でした。
表紙で白く見えていたところ(柄部分の地色)が実際はアイボリーのような
やや黄味がかった色だったので商品画像とはちょっと違うかな・・と思いました。
でもかわいいです。
 i like it i like it
キャスキッドソンの直営店でもほとんどみかけた事がないです。お手軽価格だし、人気商品なんだと思います。洋書カテゴリーでこんないいものがあったなんてスゴイ。仕事用の打ち合わせに使います。お相手の目をひくので、「それ、どこの?」なんて言われたら、1冊さしあげよう。きっとビジネスにもプラスです。
 かわいいです。 かわいいです。
代官山の路面店で買いましたが、アマゾンの方が¥安かった!(涙)
中は真っ白な罫線ノート。紙質は厚めです。リングになっているので、
今までのレシピメモを整理して、保存版ノートに仕上げ用と考え中です。
旅先の日記帳や、お取り寄せのスクラップブック、お店情報の整理にも
使えそうです…!
表表紙だけに柄があるけど、でもさりげなくかわいくて存在感のあるノート。
用途はいろいろ。長年愛用したい。
|
|

[ ペーパーバック ]
|
The Curious Case of Benjamin Button
・F. Scott Fitzgerald
【Scribner】
発売日: 2007-08-14
参考価格: 1,253 円(税込)
販売価格: 787 円(税込)

|
・F. Scott Fitzgerald
|
カスタマー平均評価:  5 5
 大人向けの寓話として面白い。 大人向けの寓話として面白い。
老人の姿で生まれ、若返って最後は赤ん坊として死ぬ男の物語が、僅か52頁の小冊子とは驚きだが、ボリュームがクオリティーを左右する訳ではないから、若さを先に失うか後から失うかという大人向けの寓話として面白く読んだ。家庭ドラマに大人びた子供の存在は不可欠だが、本書の主人公は祖父に瓜二つの皺くちゃ老人にしか見えず隠れて葉巻まで吸うのだから、その範疇を超えている。
家で子供を生むのが当たり前だった19世紀中頃、主人公ベンジャミンが麻酔薬の匂う「病院」で生まれたのは両親が進歩的だったからだという冒頭の記述が特に興味深い。医療制度の発展が少なくとも家族の一員として主人公が無事に引き取られることを後押ししたと判るからだ。もし家で出産したのなら、衝撃が強すぎて何か災いが起きたのではあるまいか。現に映画では父親が醜悪なわが子を捨ててしまう筋立てだと聞く。
著者フイッツジェラルドが生きた時代の父系重視の社会構造が反映されたのか、健在する母親が会話に登場しないのが奇妙に思える。小説とはいえ母親の戸惑いや拒絶反応を描き切れなかったのか、乳母が面倒を見る当時の習慣で母親の姿を不要と考えたのか。
父親の母校イェールで新入生登録係に疑われ、在校生に罵詈雑言を浴びせられて追い返される悲劇に見舞われたベンジャミンに、やがて<青春のときめき>が訪れる。地元ボルティモアでの仮装舞踏会で運命の女性ヒルデガードに出会ったのだ。
「細身で可憐な娘。その髪は月の光に蒼ざめ、ポーチで爆ぜるガス燈の灯を受けるとハチミツ色に輝いて見えた。黒い蝶柄の柔らかそうな黄色いスペイン製スカーフがその娘の肩口まで覆い、その足先にはスカートの縁飾りのボタンが煌いていた。」
父親をベンジャミンの兄弟だと勘違いしているヒルデガードは「年配の男性の方が好ましいですわ。大学でどれだけシャンパンを飲んだとか、やれカードの賭け事で大金を摩ったとかを得意気に話す若い人は阿呆だとしか思えませんもの。」と語る率直な娘だった。イェールでの苦い屈辱の経験から彼女の誤解を解くのをベンジャミンは躊躇った。
ヒルデガードに恋をした彼は夢見心地でダンスを楽しんだあと、「金槌と釘の次に着目すべき商品は何だと思う?」との父親からの問いに、「それはLove(愛)です。」と上の空で答えて、「Lugs(取っ手)だって?!」と父親を呆れ返させるこのやり取りがとても面白い。
最愛の女性を伴侶に迎えビジネスに邁進したベンジャミンは、ハーバードを卒業した息子ロスコーに家業(銃鉄器卸売店)を譲るが、若返って元気一杯。米西戦争に際して入隊し、大尉から少佐を経て中佐にまで昇進したり、自らもハーバードに入学し、フットボールの試合で憎っきイェールの選手たちをフィールドで薙ぎ倒し一人で七つのタッチダウンを奪う大活躍を見せたりするところは「フォレスト・ガンプ」の主人公を彷彿とさせ楽しめる。
逆回転の人生を辿ろうが、人はいつか死ぬ定めだから、得たもの(家族との思い出など)と失ったもの(別の選択肢での可能性)との帳尻がプラスである限り幸せなんだ。単純にして深遠なこんな人生哲学を本書から学び得た気がする。
|
|












 5
5 実用だけでなく、素敵な「オマケ」としての後半部分。
実用だけでなく、素敵な「オマケ」としての後半部分。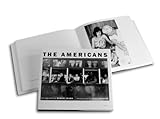
 4.5
4.5


 CDだけですよ
CDだけですよ

 見せ掛けの流暢さ、それでいいの?
見せ掛けの流暢さ、それでいいの?

